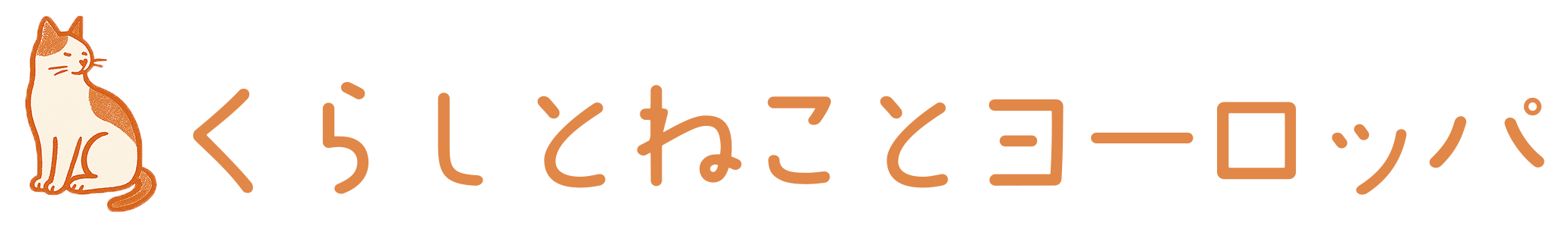フランスに住んでいて、ちょっとびっくりしたことがあります。
それは、「人口100人くらいの小さな村にも、市長がちゃんといる」ということ。
日本の感覚だと「そんな小さな自治体が市として成立してるの?」と思ってしまうのですが、
フランスでは「地方自治」の力がとても強く、暮らしの隅々まで“地元の判断”で支えられていることに気づきました。
この記事では、フランスの地方自治の仕組みや、小さな村でも市長がいる理由、
そして私自身が感じた「自治のあたたかさ」や「距離の近さ」について、移住者の目線からお話ししていきます。
フランスの暮らしをちょっと違う角度からのぞいてみませんか?
そもそも「フランスの地方自治」ってどうなってるの?

フランスというと「中央集権」のイメージが強いかもしれません。
実際、国の教育制度や医療制度は中央政府がコントロールしている面もあります。ですが、暮らしてみると驚くのが、地方自治体の裁量が思った以上に大きいということ。
フランス全体では長年かけて中央集権体制からの脱却を模索してきており、地域ごとに特性や事情を考慮した独自の行政判断ができるよう制度設計が進められてきました。
フランスの地方行政の基本構造
フランスでは、行政単位が大きく3つに分かれています:
- コミューン(commune):市町村レベル。なんと全国に3万以上あります!小さな村から大都市パリまで、すべて「コミューン」に分類されます。
- デパルトマン(département):県に相当するレベル。フランスには約100あります。教育・社会福祉・インフラ整備などの中間レベルの行政を担っています。
- レジオン(région):広域自治体。現在は13の地方圏に統合され、経済政策、地域開発、高等教育などの大枠を管理しています。
それぞれが独立して予算を持ち、選挙で選ばれた議会と執行部が存在します。中央と地方のバランスを保ちながら、住民の生活に密着した決定を行う仕組みが構築されています。
一番身近な「コミューン」
特に一番身近な「コミューン」は、実際の暮らしに一番近い行政単位です。
ごみ収集、道路整備、学校の管理、文化活動の支援など、生活に密接したサービスを提供しています。
地域に住む人々のニーズに最も近い存在として、日々の生活に直結する課題にきめ細かく対応してくれるのが特徴です。
実際に住んでみると、どれほどこの「コミューン」の存在が心強いか、実感できる場面が多々あります。
えっ?この小さな村にも市長がいるの?

フランスで驚いたのが、「こんなに小さな村にも市長がいるんだ!」ということ。
人口がわずか数十人の集落にも、しっかりと「マイヨール(maire、市長)」がいて、地域のことを日々取り仕切っています。
小さな村では、役場が郵便局を兼ねていたり、教会の隣に市庁舎があることも珍しくありません。
市長の存在意義
市長は、住民の選挙によって選ばれます。
大きな都市でも小さな村でも、民主的に選ばれた首長が存在し、行政を担うという点ではまったく平等です。
市民は日常的に市長と直接顔を合わせる機会も多く、まるで近所のおじさんのような存在として親しまれています。
市長の仕事とは?
市長の仕事は多岐にわたります。
道路や街灯の整備、地域のイベント運営、婚姻届の受理、建築許可の発行など…ときには学校の運営や消防団の取りまとめも行います。
さらに、地域の防災計画や住民への連絡体制の構築など、非常時にも欠かせない存在です。
歴史的背景にある「自治の精神」
なぜこんな制度ができたのかというと、背景には**フランス革命と市民の「自治の精神」があります。
「パリのことはパリで、村のことは村で決めよう」という考えが今も根強く残っているんですね。
特に農村部では、この精神が日常生活に深く根ざしていて、地域の共同体としての連帯感が強く感じられます。
市役所=住民の相談所みたいなもの

フランスの市役所は、日本以上に「生活の相談窓口」としての役割が強い印象です。
たとえば出生届、婚姻届、死亡届のすべてを市役所(または役場)で行います。
また、選挙の管理や税金に関する情報提供なども行っており、役所というより「暮らしのパートナー」といった存在感です。
身近な手続きの中心地
住民票の発行や公共サービスの申請、補助金の手続きなども、市役所でまとめて行えるようになっています。
特にデジタル化が進んだことで、オンラインでの予約や申請も増えてきており、若い世代にも利用しやすい行政環境が整ってきました。
市長との距離感が近い
小さな村では、市長と道端でばったり会って、「あの書類どうなってる?」と気軽に話せる距離感。
行政=お役所、というより、行政=ご近所さんという感覚に近いです。
ちょっとした悩みごとでも相談しやすく、住民と行政の信頼関係が自然と育まれていくのを感じます。
地域コミュニティの中心でもある
地域の行事やマルシェの告知、ボランティア活動の連絡など、地域の“ハブ”的存在として機能しています。
掲示板や広報紙、フェイスブックページなどを活用し、情報共有の場としての役割も担っています。
自治の力が「暮らしの安心」につながっている

フットワークの軽さが魅力
市長や村議会の判断で、小さな道路の修繕や、ゴミ収集の曜日変更などがすぐに実行される——
これは「地域で決めてすぐに動ける自治体」ならではのフットワークの軽さです。
地方特有の課題(雪かき、農道整備など)にも迅速に対応できることが、住民にとっての大きな安心感につながります。
住民の声がすぐ反映される仕組み
たとえば私の住んでいる地域では、秋に道路の落ち葉が問題になり、住民の声で清掃日を増やすことがすぐに決定されました。
こうした小さな声が届きやすいのは、議会や市役所の規模が小さいからこそ。
声をあげれば、ちゃんと誰かが聞いてくれるという安心感は、日々の暮らしを穏やかにしてくれます。
災害時や緊急時の対応力
防災情報やコロナの時の対応も、コミューン単位で細やかに動いていました。
自分たちのことを、自分たちで決めるという仕組みは、まさに「暮らしの安心」を支える大きな要素になっています。
マスク配布や食料支援など、臨機応変な対応が可能だったのも地方自治の柔軟さゆえです。
移住して気づいた「地方自治のあたたかさ」

移住者へのサポート体制
最初は外国人として緊張していたけれど、市役所の人が丁寧に書類の書き方を教えてくれたり、マルシェで会った市長が挨拶してくれたり…
そんな日々の中で「ここに住んでる」という実感が自然と湧いてきました。
移住者向けのガイドブックや、地域との橋渡し役をしてくれる住民の存在もありがたいです。
文化活動が生む交流の場
文化行事やイベントも市が主催していて、住民の交流の場になっています。
地域の小さな図書館や音楽祭、バザーなども自治体が積極的に関わっています。
移住者も気軽に参加でき、地域とつながる最初のステップとして大切な役割を果たしています。
「顔の見える行政」の魅力
誰かのために動いてくれる「顔の見える行政」は、移住者にとって大きな安心材料です。
問題が起きたときも、すぐに相談できる環境が整っています。
書類だけではない、人とのつながりがあるからこそ、「ここで暮らしていける」と感じることができるのです。
まとめ|市長がいる村の意味ってなんだろう?

自治は暮らしの土台
日本では「市長」というと大きな都市の首長をイメージしがちですが、フランスでは「人が住んでいればそこに自治がある」という考え方が根付いています。
小さな村に市長がいるのは、「誰かの暮らしを、誰かがきちんと見守っている」という証。
日々の暮らしのひとつひとつが地域に見守られている安心感は、都市にはない魅力です。
移住して実感した「ちいさな自治」の価値
フランスの地方自治を知ることは、「暮らしを自分たちでつくる力」に気づくことでもあります。
移住者としてこの制度に触れた今、私はこの「ちいさな自治」に、とても大きな価値を感じています。
「不便」や「不安」がある分、地域で支え合う仕組みがちゃんと生きている。
その姿はこれからの社会のヒントになるかもしれません。
最後に|地方自治が育む、豊かな暮らし

暮らしの中にある政治のかたち
地方自治は、遠いものではなく、日々の生活そのものに関わっている存在です。
住民一人ひとりの声が届く場所があり、それを受け止める仕組みがあるからこそ、心地よく暮らせるのだと実感しています。
小さな決断が積み重なって、地域の未来が形づくられていくのです。
これからフランスで暮らす人へ
もしフランスの地方に暮らす予定があるなら、ぜひ市役所や地域のイベントに顔を出してみてください。
行政がぐっと身近に感じられるはずです。
そして、その身近さが、安心や信頼、暮らしの豊かさへとつながっていくのだと思います。
行政の話が他人事でなくなる、その瞬間にこそ、本当の「暮らし」が始まる気がしています。